最近では、AIや情報過多の時代において、「問いを立てる力」や「深く考える力」が求められるようになってきました。そんな中、全米トップ進学校「スタンフォードオンラインハイスクール」では、哲学が必修科目とされています。
なぜ哲学?どうして今の子どもたちに必要なのでしょうか?
スタンフォードオンラインハイスクール校長であり、哲学博士でもある星友啓先生は、「哲学思考」がクリエイティブな発想力を育て、これからの時代を生きるための土台になると語ります。
この記事はこんな方におすすめです
- 子どもの「創造力」や「思考力」を伸ばしたいと感じている方
- 「考える力」を育てるには、どんな関わり方が大切なのか知りたい方
- 子どもと一緒に、日常の中でできる会話や問いかけの工夫を探している方
- 海外トップ校が取り入れている教育や、スタンフォード式子育てに興味がある方
本記事の出典動画
YouTubeチャンネル「PIVOT」より以下の動画の内容をまとめています。
📺【クリエイティブ脳の育て方】全米トップ進学校では必修科目「哲学」のススメ/心のスキマ時間が思考力を育てる/現代の親が知るべき脳の仕組み/スタンフォードオンラインハイスクール校長が徹底解説
出演:星友啓(スタンフォードオンラインハイスクール校長)
岩崎由夏(YOUTRUST代表・二児の母)
国山ハセン(PIVOTプロデューサー・一児の父)
なぜ今、哲学が大切なのか?
「哲学」と聞くと難しそうなイメージがあるかもしれません。でも本来の哲学とは、「どうして?」「なぜ?」と疑問を持ち、それを深く考えていく営みです。答えが一つに決まっていない問いに向き合い、自分なりの視点を探っていく。このプロセスこそ哲学であり、思考力や想像力の基礎をつくります。
また、子どもが中高生になると、「決められたルールの中でうまく立ち回る力」が求められる場面が増えていきます。テストで正解を出す、与えられた枠組みで成果を出す――それ自体は大切なスキルですが、それだけではこれからの時代を生き抜くには十分ではありません。
AIが台頭し、正解がすでにある作業をどんどん自動化していく中で、人間に求められるのは「まだない問いを立てる力」や「当たり前を疑い、問い直す力」です。
目に見える成果だけではなく、目に見えにくい「問い続ける力(=哲学思考)」を育てる――そんな子育てが、これからの時代にますます大切になってくるのではないでしょうか。
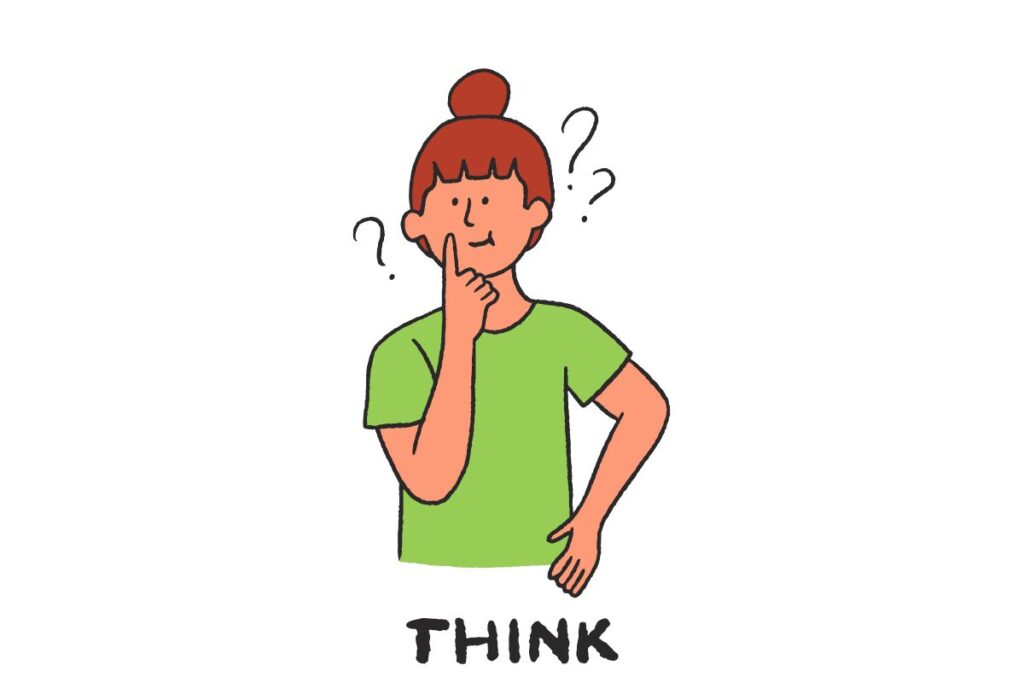
親が“哲学思考”のロールモデルになるには
哲学思考は、教科として「学ぶ」よりも、日々の暮らしの中で「育つ」もの。だからこそ、親自身が考える姿勢=ロールモデルになることが重要です。
▽ 積極的に見せるべき態度
- 問いを立てて考える:「どうしてこうなってるんだろう?」と親自身が疑問を投げかける
- 根拠や理由を考える:「私はこう思う。なぜなら〜」と理由を添えて話す
- 相手の意見を親身に聞く:「なるほど、それもいい考えだね」と受け入れる姿勢
▽ 避けるべき態度
- 0か1かで考える:「正しい or 間違い」で片付けない
- ドグマ(固定観念)を押し付ける:「普通こうでしょ」と決めつけない
- 知ったかぶりをする:「知らない」を素直に認めることで学びが深まる
年齢別!哲学思考を育てるトレーニング方法
星先生は、子どもの発達段階に応じた哲学思考のトレーニング法も紹介しています。日常の会話の中で無理なく取り入れられるものばかりです。
● 4歳からの哲学思考①:たとえば何?
- 「赤くて四角いものって何があるかな?」
- 「うるさくて丸いものってある?」
▶ 解釈力・分析力・評価力・推論力が育つ
▶ 抽象的な概念から具体的なイメージを導く練習
● 4歳からの哲学思考②:同じ探し
- 「りんごとメロン、どこが同じかな?」
- 「自転車とパン、何か共通点あるかな?」
▶ 解釈力・分析力・説明力が育つ
▶ 具体から抽象へ思考を広げる
● 小学生向け:目的探し
- 「どうして信号があるんだろう?」
- 「学校の机って、なんでこの形なんだろう?」
▶ 物事の理由や背景を探る力を養う
▶ 根拠をもって考える思考の土台に
● 中高生向け:クリティカルシンキング
- 「学校ってどんな場所?」「もし校舎がなかったらどうなる?」
▶ 常識や前提を一度壊して考える練習
▶ 変化を受け入れる創造力・柔軟性を育む
▶新しいものを生み出すマインドセットを作る
“ぼーっとする時間”が創造性を育てる
そして、意外にもクリエイティブな脳を育てるために大切なのが「ぼーっとする時間」です。スマホや動画などの刺激が絶え間ない現代、子どもたちは「何もしない時間」を失いつつあります。
しかし、脳が“何もしない状態”のとき、脳では「デフォルトモード・ネットワーク(DMN)」という領域が活性化していることがわかっています。このネットワークは、記憶の整理、自己との対話、未来の想像、創造的なひらめきなどに深く関わっています。
そのため、脳が“何もしない状態”のときこそ、過去の記憶や思考を統合し、新しいアイデアが生まれやすくなります。
親が「退屈な時間」や「何もしていない時間」を“ムダ”と見なさず、大切にしてあげること。それが、子どもの思考力や創造性を伸ばす大きな鍵になるのです。

編集後記(感想)
2歳の頃から、わが子は毎日のように「なんで?」「どうして?」と問いかけてきました。
「なんで電柱に黄色いのが巻いてあるの?」
「どうしてこのおもちゃは困った顔してるの?」
「風はどうして吹くの?」
「ほかには?」「なんでなの?」
慣れない当初は、あまりに多い質問に辛くなることもありました。でも、この動画をみてすごく貴重な「問い」だったのだと気づきました。
これからはもっと親も考えることを楽しみながら、哲学思考をなくさないようにしたいと思いました。
星先生もおっしゃっていたように、中高生になると「決まった枠組みの中でうまくやっていく」ことが求められる場面が増えていきます。
でも、そこにとどまらず、新しいものを生み出せるマインドセットや、問い続ける力も持ち続けてほしい。
そのためにも、幼少期からの問いかけや対話を大切にして、「考えるって面白い」と思える土台を育ててあげたいと改めて思いました。
~星友啓先生のお話をまとめた他の記事ほこちら~
星友啓先生の関連書籍はこちら↓(アフィリエイトリンクを使用しています)



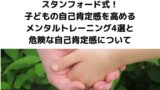
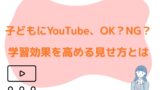





コメント